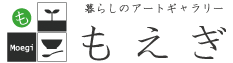南会津で活動する木彫漆芸作家の藤原さんは大阪生れ。小学校で日本の伝統的な工芸の魅力に目覚め、高校時代にはすでに"漆について勉強したい"と思っていたそうです。進学した金沢美大の4年間で、さまざまな漆の技術を習得。卒業後は働きながら、コンペのための作品を制作したり、ワークショップの講師を務めたりして、漆と木工の仕事をつづけられました。37歳で独立。現在は、福島県南会津町に自宅兼工房を構え、豊かな自然とゆっくりと流れる時間の中で、制作に励む毎日を送られています。
修行経験なし。漆の技法は学校と実践で学びました
僕が生まれ育ったのは大阪・柏原です。古墳が多く、奈良などにも近かったため、歴史好きの父親に連れられて、よく古墳や名所旧跡・神社仏閣を訪ねました。小さい頃からもの作りが大好きで、小学校3年生の時には鷹が飛び立つ構図のレリーフを制作。6年生の時には金閣寺と銀閣寺のジオラマ風の作品を作り、周囲を驚かせていました。漆に興味をもつようになったのは高校時代です。1年間浪人して、京都の某私立の美術大学に入学。そこで立体造形を学んでいたのですが、漆への思いが断ちがたく、京都の美大に通いながら勉強をつづけて、金沢美術工芸大学に合格しました。伝統工芸を学ぶには最適の環境であるこの学校の4年間で、漆の基礎からひととおりの漆芸技法を学びました。
奥行きのある艶感とでも言うのでしょうか。なめらかでぬくもりがある、漆独特の質感が好きなんです。それは他のものでは代用できない特別のもの。振り返れば、日本の伝統工芸の世界の平文とか、螺鈿とか、漆でしか表現できない美の世界に魅かれたことが、漆そのものに興味をもつきっかけになった気がします。
「とにかく、作りつづけろ」ー 恩師の教えを守って
学校を卒業してすぐに岐阜の家具メーカーに就職し、家具のデザインと設計を担当しました。28歳の時に、大学時代の後輩と結婚。妻が福島出身だったため、結婚を機にサラリーマン生活に終止符を打ち、福島県に移り住みました。妻の実家がイワナの養殖をやっていたので、昼は養殖の仕事を手伝い、夜はコンペのための作品を作り、週末は漆のワークショップの講師に出かける...そんな生活を8年ほどつづけました。

僕らの学生時代はバブルの絶頂期。望めばかなり名の通った企業にも就職できたんです。漆を学んだ仲間もいい企業に就職する者が多く、漆を一生の仕事にしようという学生はとても少ない状況でした。そんな中で、恩師から言われた「就職しようが何をしようが、とにかく作りつづけろ」という言葉が胸を打ちました。以来現在まで、僕はその言葉を守っています。
コンペのための作品から生活的な工芸品へ
独立する前に作っていたコンペのための作品は、現代クラフト的なオブジェっぽいものでした。出品しては、また制作する。そんなことを何年か繰り返していたのですが周囲に理解者が少ないんです。会津は山奥で、昔から脈々と人々が伝えてきた木工品があります。ある時から、地域の手仕事と繋がっていけるような日用品、ふだんあったら楽しくて豊かな気分になれる...そんな地元の人にも分かりやすい、生活のなかで生きる工芸品を作ってみたいと思うようになりました。

木彫漆芸作家として独立することを決め、南会津町に引っ越して来ました。ここを選んだ理由のひとつは、長年ワークショップの講師を務めさせていただいた材木屋さんがあったこと。北海道の木や東北の広葉樹が豊富で、材料の仕入れができるお店が近くにあれば、つくり手としてこれほど心強いことはありません。長年つづけたワークショップを通して知り合いも増え、南会津をよく知っていたこともあります。またそれ以上に、南会津の豊かで厳しい自然の中に身を置いて、作品作りに向き合いたかったことが大きいです。
自分が楽しんでいられるよう、人として成長していきたい
僕が作品を作る上で大切にしているのは、手彫りならではの造形とノミ跡の味わい、そして拭き漆の風合いです。ほとんどの作品を何度も漆を摺り込んでは拭き上げる技法「拭き漆(ふきうるし)」で仕上げています。「拭き漆」なら木目がつぶれることなく表れ、原料の木がもともと持っている美しさや面白さをそのまま生かせます。傷などが目立ちにくく気軽に使え、手入れがしやすい点でも、日常使いの工芸品に向いていると思います。
50歳になりました。よい作品、人に喜んでもらえるものを作っていきたいです。最近特に思うことなんですが...自分が楽しんでいないと、仕事に気持ちの乱れが表れる気がするんです。日々の生活がうまくいっているとか、ご近所と仲良くやれているかとか。それらすべてを含めて、まずは自分が楽しんでないと。テクニック的なものはもちろんですが、人として、これからもっともっと成長していきたいです。
※平文(ひょうもん)・・・別名、ひらもん。漆器の加飾法のひとつ。金銀などの薄板を文様に切って漆面にはり、漆で塗り埋めてから、その部分を研ぎ出すなどして文様を表す。奈良時代に中国から伝わり、平安時代に盛んに用いられた。
※螺鈿(らでん)・・・貝殻の真珠色に光る部分を磨いて薄片にし、種々の形に切って漆器や木地の表面に嵌め込んだり、貼りつけて装飾する工芸技法。平文と同じく、奈良時代に中国から伝えられ、平安時代には蒔絵にも併用された。
福島県南会津町
- 1965(昭和40)年
- 大阪府生まれ
- 1990(平成2)年
- 金沢美術工芸大学 産業美術学科工芸デザイン専攻漆教室卒
- 1994(平成6)年
- 福島県に移住
- 1995 (平成7)年
- 世界・木のクラフト展 審査委員長賞受賞
国際デザインフェアINみやぎ 入選
'95高岡クラフト展 入選 - 1996 (平成8)年
- 朝日現代クラフト展 入選
'96高岡クラフト展 審査委員賞受賞 - 1999(平成11)年
- 世界・木のクラフト展 理事長賞受賞
- 2000(平成12)年
- '00高岡クラフト展 入選
- 2001(平成13)年
- 世界・木のクラフト展 理事長賞受賞
- 2004(平成16) 年
- '04高岡クラフト展 入選
- 2006 (平成18)年
- 南会津に移住